【 レンガDIY入門(初心者ガーデニングの素材選び):種類 】 | |
| 今や庭ガーデニングDIYで欠かせない存在がレンガですね。花壇にしてもステップ、BBQ、などなどレンガを多用したガーデニング作品は素敵なものが多いですよね。 そんなレンガについて整理してみると、まず種類は、平面に並ベる作業用の「敷きレンガ」と、塀や壁など積み上げていく建材用の「積みレンガ」に大別されます。 ガーデニングでレンガワークを計画する場合は、図面のラフスケッチを描いて、レンガの個数を計算しておくと、後でレンガが余ったりといった心配がなくなります。 | |
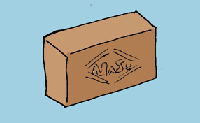 |
<新品レンガ> 今のように庭造りDIYやガーデニングが定着する前までは国産の赤レンガ(※規格は210×100×60)が基本でした。形のくずれていない長方形なのでキッチリした作品が自作できますが、個人的には温かみに欠ける気がしますので我が家の庭ではあまり使用していません。ただ、欧米産の特徴あるレンガが数多く販売されていたり、最近ではマレーシア産などの安価なタイプも多くなったので、庭の雰囲気や目的に応じて購入されれば良いでしょう。 耐火レンガの場合にはブランド名が刻印されているものも多く、DIYではバーベキューコンロなどに利用します。 |
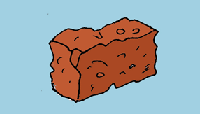 |
<ナチュラルレンガ> 自然の風合いがあり、温かみある作品を自作できるレンガです。形や大きさが揃っているわけではなく、多少ボロボロと崩れてしまうこともありますが、崩れた形そのものが逆に魅力となって、庭の雰囲気に合わせガーデニングでも好んで使いたいレンガだと思います。 |
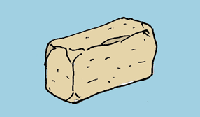 |
<アンティークレンガ> 中世ヨーロッパのお城の壁に使われているような“古風”な感じのレンガで、ラフな作品を自作するのに適していて、多くのガーデニング装飾に使われます。この素材は素人DIYであっても落ち着いた古風な作品に仕上がるため、私もこのレンガを庭の中で一番多く使用しています。 |
 |
<ピンコロ石 サイズがコンパクトなので、いろいろな敷き模様を作ることができますが、その分手間もかかります。ホームセンターで売られているものの大半は御影石で出来ているので、どうしても和の雰囲気になりがちですが、アクセントとして洋風の庭に敷き詰めても素敵な庭になります。 |
 |
<積みレンガ> 強度を保つために開けられた穴に、鉄筋を入れてからモルタルを流し込むことで、強度を増すことができるレンガです。もちろん、塀などの一番上の部分は、穴の開いていない笠木タイプのレンガを使用します。 |
 |
<敷きレンガ> 正方形の敷きレンガは、その硬さが特徴で、ガーデニングでは強度を必要とする庭の場所(ステップなど)に使えます。 |
 |
ホームセンターで販売されているレンガも最近では種類が豊富になってきましたし、個性的な庭造りを目指しさらに特徴的なレンガが欲しいならインターネットで欧米産の素敵なレンガも手に入ります。 ただ、ホームセンターで購入したものを自宅へ運ぶのも意外と大変で、(別途、配送費を払うのも勿体無いですし)大量に購入した場合には軽トラックを借りて自宅へ運び、自分で何往復もしながら庭へ運び入れていきます・・・コレ、かなり重労働ですよ。 |
【 ガーデニングDIY実践:レンガ積み方/敷き方の基本 】 | |
| 積み方の手順とリズム | 難しいようで単純、単純だけど難しいのがレンガ積みの作業です。街を歩いていてもプロの職人が手がけたような花壇や外壁と、明らかに素人の人が積み上げたものとでは、誰の目にも歴然とした差が認識できます。 ただ、機械的に正確に積み上げられたものが全て美しいかといえばそうでもなく、使うレンガの素材や“手作り感”の残る積み方での作品の方が暖か味があって素晴らしく思えるものです。 基本的にレンガ積みの作業は、それだけでなくモルタルの硬さ/柔らかさの加減やコテの使い方など“経験的に慣れる”必要がありますが、小さな作品から徐々に積み方の練習すれば、それほど時間をかけることなく慣れていきますので、まずは下記の積み方の基本をしっかりご理解ください。 |
 |
<レンガの積み方-手順1> レンガワークで庭にDIY作品を造る時、作品以上に気を配る必要があるのは実は基礎となる部分です。基礎がしっかりしていないと出来上がったときに表面に凹凸ができて、美しく仕上がらないばかりか、レンガ積みの作品が倒れたり傾いてしまう可能性もあり、見た目だけでなく子供達にも危険な庭になってしまうからです。 造る庭の場所が決まったら、作品の寸法の1.5〜2倍程度広く、10cmくらいを水平に掘っておきます。そこへ細かい石やコンクリート片を敷き、ダンパー(枕木など表面が水平で重い大きな木でも可)などで突き固めておくことが必要です。 |
 |
<レンガの積み方-手順2> 突き詰めた土の上にモルタルを敷いて固めた後は、もともとの基礎部分が水平になるように水平器で測って平らにしておきます。 そして出来上がった基礎の上にレンガをモルタルで固定しながら置いていきます。 ※最初のモルタル面が水平ならば、置かれたレンガもほぼ水平になっているはずです。 積み方として慣れた方は最初の段階から水糸を引いて、水平を取りつつレンガを積んでいかれます。初心者ではなかなかしない面倒に思える作業ですが、特に大きな作品や幅の広い=長さのある作品(花壇など)では、それぞれ一番端のレンガの高さが違ってくることもありますので、面倒くさがらずに水糸で水平を測るようにした方が良いでしょう。 逆にそれほど幅のない作品では隣同士のレンガの高さを水平器などで合わせてやる程度でも大丈夫です。 |
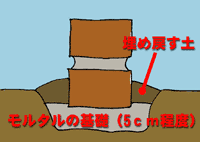 |
<レンガの積み方-手順3> 勿論、造る作品によって基礎の構造は変りますが、一般的な構造は左図のようになります。 よく突き固めた地面の上に5cmくらいにモルタルを敷きます。そして、このモルタルが乾いてしまう前に1段目(一番下)のレンガを固定すれば、おのずとしかり安定したDIY作品が出来上がることになります。 |
 |
<レンガの積み方-手順4> 一般的に横や縦長だけの作品は倒れやすくなりますので、(庭の構造や広さにもよりますが)上から見て円弧またはL字型の作品にすることが重要です。単なる横長の壁のようにレンガを積むことなく、そのようなDIY作品であっても基礎またはデザインとして下部分を極力広範囲に確保するようにしましょう。 この手のホームページやDIY教本に記載されていることですが、レンガを積む前の注意としては積む前にレンガを濡らしておくことがホントに重要です。水に浸したレンガはモルタルとよく馴染み、接着しやすくなります。理想としては作業をする半日前くらいから浸しておくのが良いようです。 |
 |
<レンガの積み方-手順5> 作業が進みレンガが高くなってくると後でまとめて水平を調整するなんてことはできなくなりますので、レンガの水平は一個一個積んでいく度に、丁寧に/素早く水平器を使って測ります。 水平が狂っているようであれば、ゴムハンマーやコテの取っ手部分などを使い、コンコンとレンガの水平を微調整していくことが必要です。こした積み方を繰り返し行うことで、作品の完成度が大きく違ってくるので日数をかけてでも段々に積んでいきましょう。 |
 |
<レンガの積み方-手順6> 初心者のうちは1段積んだくらいで・・慣れてくれば2〜3段積んだあたりで、目地ゴテを使ってレンガ間のモルタルを綺麗に整形していきます。 目地の整形が終わったタイミングで(まだ、モルタルが乾ききっていない状態の時に)、水で濡らしたスポンジを硬く絞ってレンガの表面に付いた汚れ(モルタル)を丁寧に拭き取らなければなりません。これをしないと乾燥した後でレンガの表面が白っぽく汚れてしまい、なかなか落とせない状態になりますので注意してください。 ・・・私も最初に作った時に、この作業のタイミングやスポンジの濡れ具合がわからず、結局はレンガを汚していましたが、“かなりキツク絞った”状態のスポンジで、“丁寧に何度も拭く”ように心掛ければ大丈夫です。 |
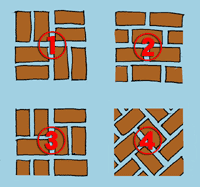 |
レンガの積み方ではなく庭やアプローチへの敷き方のパターンもいくつか紹介しておきましょう。レンガを敷き終わったときの見栄えや、他のDIY作品とのアクセントの違いなど、敷き方一つでも庭に変化が付けられます。 <主なレンガ敷きパターン> (1)バスケット (2)ランニングボンド (3)ハーフバスケット (4)ヘリンボーン 庭のコーナーかアプローチなのか・・等の場所によって使い分けると良いでしょう。 レンガ敷きの場合には実はあまり“勾配”は気にしなくて良いのです。勿論、下がコンクリートなど透水性が無い場合は別として、レンガそのものには透水性があり、雨が降っても目地がレンガを通って地中へ吸い込まれるため、立水栓などよほどの洗い場でもない限り、あえて傾斜は必要ありません。 |
【 ガーデニングDIY実践:コンクリートブロックの積み方 】 | |
| 正確な位置あわせが必要なコンクリートブロック積み | レンガのようにある程度ラフに積んだ方が味が出る素材と違い、コンクリートブロックは、規格寸法がはっきりしているため「正確に位置を合わせて積んでいかないと見た目に悪い」完成度となります。 そうは言ってもモルタルとの接着性、加工の手軽さなどの点から、コツさえつかめば初心者の方でも施工のしやすい材料ともいえます。また、コンクリートブロックは、それ自身を積みあげて門柱、塀、花壇などをつくるだけではなく、レンガ、タイルばりなどの土台としても多用されます。 |
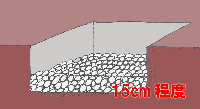 |
<コンクリートブロックの積み方-手順1> まずはコンクリートブロックを積む土台部分を掘ります。基礎となる砕石の厚さを5cm、基礎コンクリート(※捨てコン)を10cm、合計15cmはみておきます。 |
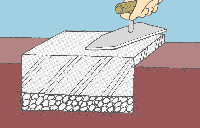 |
<コンクリートブロックの積み方-手順2> 捨てコンは地面の高さより、やや高めに打ち、表面を平らに仕上げておきます。 |
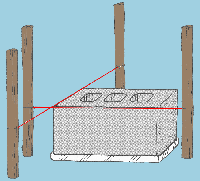 |
<コンクリートブロックの積み方-手順3> 水平を取るために柱(※遣形といいます)を立て、水糸を張れるよう「同じ高さの位置」にそれぞれ印を付けておきます。※水平は普通は水盛管という道具で取りますが、無いときはバケツと透明ホースで代用できます。 そうして、水盛りのレベルを基準にして一段目のブロックの高さを決め、水糸を張ります。このとき水糸はブロックの角に合わせておくのがコツです。 |
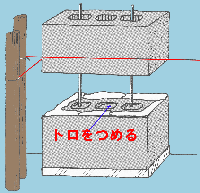 |
<コンクリートブロックの積み方-手順4> 鉄筋を入れてコンクリートブロックを積み上げていきますが、その際に水糸は段ごとに合わせて張り替えます。 ※3段程度積むごとに、「下げ振り」で垂直を見ておくと良いでしょう。 このようにコンクリートブロックを美しく積むには、水平と垂直を小まめにチェックし作業を進めましょう。 |
【 ガーデニングDIY実践:レンガDIYに使う工具 】 | |
| ガーデニングをはじめると必ずと言ってよいほどレンガを使ってDIYで花壇やステップを造りたくなるでしょう。でも、実際に作業をはじめようと思っても、道具が無かったり、何を揃えればいいか分からなかったり・・と、初心者には意外と“最初の一歩”が踏み出せないもののようです。 基本的にはレンガさえあれば並べ置きするだけでも立派なガーデニング装飾が出来ますし、頑丈に固定したい時にはじめてモルタルで積んでいけば良いのです。沢山のDIY作品を造る予定がないなら、ほとんどの工具は“家庭用品で代用”できるものと思いますので購入の必要はありません。 | |
| <素人DIYでも絶対に必要なコテ> 実はコテ | |
| <安価なもので構わない水平器> DIY作業の必需品と言えば、庭に限らず屋内DIYでも役立つ“水平器”ということになります。また、レンガ作業にはこの水平器 ただし、大小の水平器を購入する必要はなく、広い面の水平を測る必要がある時などは、長めの真っ直ぐな木材や金属棒に水平器を固定してしまえば、充分広範囲でも使える水平器になってくれます。 | |
 |
レンガDIYでも、それほど多くの作品を造らないのであれば「タガネ ただし、大きな作品や数多くの作品を造る予定があるのなら、タガネでの加工作業はかなり重労働になるので、下段の電動工具を購入されることをお勧めします。 |
 |
レンガ加工には素人DIYであってもディスクグラインダー この電動工具は高速で回転しレンガを切断できますが、音もさることながら粉塵が目に飛び込んできますので、あわせてゴーグル |
| その他のDIY工具 ・レンガ作業道具 |
その他にも“必需品”といえるモノが幾つかあります。 ・スポンジ 素人DIYのレンガ作品で失敗するのが、完成した作品が後で白っぽく汚れてしまうことです。作業中もこまめにモルタルの汚れを拭き取る必要があり、水で濡らしたスポンジを固く絞って使ったり、タワシでこすり落とすなど注意深く作業するようにしましょう。 ・トロ舟 ・水糸(庭の広範囲で水平を測る場合) ・・勿論、全て揃える必要もなく、身近なもので代用できれば素人DIYには充分なのです。庭の大きさや作品数を考慮し無駄な投資をしないようにしましょうね。 |
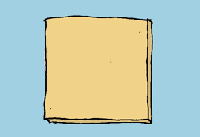 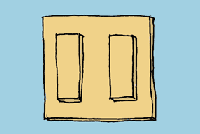 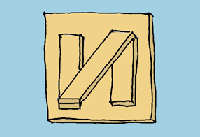 |
代表的な自作道具:コテ板の簡単な作り方です。 (1)一辺30〜35cm程度の合板、またはベニヤを1枚用意します。 (2)適当な長さに切断した角材を合板に打ち付けます。 (3)斜めに切断した角材を打ちつけ「取っ手」にします。このときに手で握る部分をヤスリがけしておかないと使用しにくいので、ちゃんと磨いておけば手作りコテ板の完成となります。 |