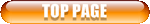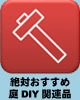【 水が流れる小さく素敵なレンガウォールDIY 】 | |
 | |
| 小型のレンガウォールをDIYで造ることにしました 花壇の中に最初に全体の大きさを決定し、土台部分にレンガや平石を設置しました。実は最も気をつかったのはこの部分でして、「あとで大きな壷(一番下の受け皿)を置くための土台」はレンガを並べたりすると“水平にモノを置けない”=“グラグラする”可能性があるため、最初からあらかじめ大きめの平石を購入し、それを水平に固定することにしました。 | |
 | |
| レンガウォールの背面の目立たないところに外部へ繋がる空洞を造ることにし、これによって雨降りの日に土台部分に水が溜まらないようにしています。 | |
 | |
| 下の受けには大きな壷(・・穴の開いていないタイプを探すのが意外と大変でした)を置き、レンガを積む高さを現物で測りながら作業しています。 | |
| 壷の高さまでレンガを積んだところで、ステンレスのフックを2箇所に挟み込み、またその上にレンガを積んでいきます。このフックは、オシャレなチェーンを購入して、チェーンで壷を固定させるための工夫です。これで台風などの強烈な風が吹く日でも壷が転倒することがないので安心です。 | |
 | |
| (一番上に設置する予定の壷から)真ん中の受け皿(自作)へ、それから更に一番下の大きな壷へと段々と水が落ちていく仕組みなので、モルタルで固定する前に何度も実際に水を入れつつ“落下する流れや位置”を確認しています。
水を循環させる仕組みの場合、強い風が吹く日であっても(風で流されて外へこぼれないよう)確実に下の受け皿や壷に水が落ちていく必要があります。風のある屋外に設置する場合、少しずつでもこぼれてしまうと半日も経たずに水枯れが起こるための対策です。 | |
| 一番上の小さな壷も、目立たないようにフックと真鋳の針金で固定しています。 水を循環させているので当然裏に穴を開け、そこからホースを入れています。 「陶器の穴あけ」には木工用のドリルを使うのですが、そのまま作業すると割れてしまう可能性があるので、あらかじめ穴を開ける箇所全体を水に半日程度浸しておきます。そうすることで、ドリルをあてても壷が割れることなく作業できるのです。 | |
 | |
| 小さなモーターで水を循環させ、一番上の小さな壷から徐々に水が落下するレンガウォールDIYの完成です。 ・・水の流れる音がして癒しの空間になりますよ。 | |
| 最上段の壷から水が落ちてくる四角いレンガ調の受け皿は、実は東急ハンズで購入した「樹脂粘土」を使って自分で成型して造ったものです。自作のパーツなので、全体の大きさに合わせて造ることが可能なのですが、乾燥させた後でも大量の水には弱いようでしたので、車修理用のパテを購入し樹脂粘土の上からコーティングしてから塗装しました。 | |
| 循環水の出口となるレンガウォールの一番上の壷から水が出てくる部分は、透明のホースを内側から針金で固定しています。 | |
 | |
| 蚊などの発生を防ぐため(こちらには金魚ではなく)磨いた10円玉を数枚入れてあります。実は10円玉の“銅”が、そうした蚊などの発生を防止する働きがあるそうです。ちなみに10円玉を磨くにはコカコーラなどの炭酸飲料に一晩浸けておけばピカピカになります。 | |
| レンガウォール横のスペースには装飾も兼ねて、四角いレンガを円形に配置し、鉢置き台を造りました。単純にレンガを並べただけですが、全体的なバランスとしてのアクセントにもなっていると思います。 | |
【 後日の補修作業DIY 】 | |
| レンガウォールDIY完成後しばらくしてから樹脂粘土が柔らかくなってしまいました。どうやら完全な防水性能はないようで、長年の風雨と流水によって徐々に硬化していた表面が削り取られていたらしいのです。 知人に聞いたら「プラモデル屋さんで売っているエポキシパテなどを使えば、完全に硬化した後はヤスリがけできるほどで、粘土のように成形も楽だ」ということでした。 今回の補修では100円ショップで透明の容器と透明のホースを購入し、ハンダを使って穴を開けたり・・容器を溶かしながらホースと接合させたりし・・完全防水の処理を行いました。 | |
| (1)は、透明のポリ容器に端に穴を開けて加工しました。 (2)は、透明のホースをナナメにカットし、勢いよく壷に水が注がれるようにしました。 | |
| もともとあった容量に収まるサイズの透明容器を100円ショップで調達しました。その四隅の一つにハンダで溶かしながら穴を開け、排出口で繋げています。 もちろん、容器がピタリとはまる大きさのわけはないので、隙間にはモルタルを積め、その上からペンキで着色しています。 | |
| 排出口には透明のホースを(前述の)透明容器と接続し、その上からやはりモルタルとペンキで装飾しています。接合部分はハンダで溶かしながら透明容器とホースを繋ぎますが、熔け落ちてしまった部分は後からコーキング剤を塗って防水処理しました。 ここの部分の注意点はズバリ「水切れ」の良さです。流れ出てくる水が垂れてしまうと、下の壷に落ちずにレンガウォールの壁側にしたたり落ちてしまいます。ヤカンのお湯が勢いよく注がれるように、水切れの良さを何度も確認しつつ調整してから最終設置するようにしましょう。 | |