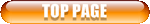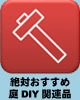【 雑草対策 】 | |
 | |
| <雑草の種類> ガーデニングで悩ましいのは雑草対策ではないでしょうか。気付いたらあたり一面の雑草で景観が変ってしまうことも多々ありますので、我が家でも年中雑草対策に追われています。 一言で雑草といっても多種にわたり、「イネ科」の雑草は多年草のものが多く、地下深く根を張り大きく成長します。「トクサ科」の雑草は根を張る範囲が広く、抜いても抜いても次々と生えてきて除去するのも困難です。「ゼニゴケ科」は日陰を好む雑草で基本的に除草剤は効きません。雑草の中には花粉症の原因になる雑草もあるので、面倒でもしっかりメンテナンスを欠かさないようにしましょう。 | |
| 必ず根元から抜く | |
| <表面だけ取り除いても全くの無駄> 庭木が埋まっていたり花壇の傍では「除草剤」は使えません。ですので、雑草対策として一番手っ取り早いのは「抜く」ことです。そしてそのコツは“草の地上部だけでなく根元まで必ず抜く”ことが重要です。それには根が充分に張る前の小さな状態の時に発見するよう心がけ、大きくなってなかなかうまく抜けない場合には雨上がりの土が湿っている時に抜くと有る程度抜きやすいはずです。 道具としても除草フォークなど専用のものもありますが、食卓で使っていた古いフォークを使っても充分ですので、先を地面に対して垂直に刺すようにし根っこから抜き取るようにしましょう。 花壇など土のある場所にはバークチップなどを撒いておくのも有効です。一定量を土の表面に撒いておくと雑草の発生が防止できますが、植え替えの度に土と混ざるので随時補充していくことも大切です(※バークチップは古くなると土と混ざり肥沃になるのでメンテナンスも楽ですよ) | |
 | |
| <砂利などの下には防草シートを張る> 最近ホームセンターのガーデニングコーナーなどで市販されている遮光シート/除草シートを張るのも効果的です。我が家も芝生から玉砂利の庭に変えた際に、その下地として除草シートを敷き詰めました。 手順としては、しっかり除草した後に表面を平らにならし、その上にシートを張ってワイヤーピンで固定してから砂利を敷いていきました。除草シートは黒色で水は通すが光は通さないので、雑草が発芽しないのです。 ガーデニング後のメンテナンスを軽減したいならこの対策をオススメしますね。 | |
【 害虫対策 】 | |
 | |
| <効果的に薬剤を使う> 害虫には殺虫剤を使いますが、草花の病気には殺菌剤を使うことになります。 殺虫剤は直接虫にかからないと効果が期待できないので、日ごろのメンテナンスの際に葉の裏や地面に糞が落ちていないかチェックすると良いでしょう。いずれにせよ早期発見がポイントです。 殺菌剤は風のない日の午前中に散布し近隣へ飛散しないよう注意をしましょう。ただ、一度病気になってしまうと1回の散布で完治することはないので、根気よく退治するようにしてください。 | |
| 【害虫】 アブラムシ | |
| 新芽や葉の裏にぎっしり発生します。モザイク病などのウイルスを広げてしまう害虫なので薬剤散布など早めに手を打つべきです。 | |
| 【害虫】 ハダニ | |
| 白い点が葉に広がっていたらハダニの可能性があるので、葉の裏に寄生していないかチェックしましょう。実は薬剤でなくても水で洗い流すだけで駆除できます。 | |
| 【害虫】 カイガラムシ | |
| 庭木などに貝殻のような形の虫が無数に寄生します。樹液を吸って木の生育を妨げるので、歯ブラシをつかって擦り落とします。 | |
| 【害虫】 ナメクジ | |
| 夜に出てきては葉や花を食べてしまうので見つけたらスグに捕殺します。薬剤散布のほか、ビールにも誘引されて集まります。 | |
| 【害虫】 ヨトウムシ | |
| 通称イモムシ。見つけ次第に捕殺するか、オルトランなどを地中に入れても効果的です。 | |
| 【病気】 うどんこ病 | |
| 葉の表面に粉状の白い斑点ができる病気です。早めの薬剤散布と風通しのよい場所で管理するようにします。 | |
| 【病気】 モザイク病 | |
| 葉や花などが縮んでしまったようになりまだら模様になります。前述のアブラムシなどが媒介しますが、病気に対し通用する薬剤はありませんので広がる前に焼却します。 | |
| 【病気】 炭そ病 | |
| 葉に褐色の斑点ができます。斑点病はほかにもありますが、(共通して)被害を受けた葉を取り除く対処が必要です。 | |
| 病害虫駆除の豆知識へジャンプ | |
| 病害虫対策詳細へジャンプ | |