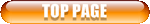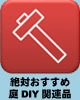【 植物に関する病気 】 | |
| 病気の種類 | |
| 花壇や庭づくりをした後の維持管理において、ガーデニングの大敵である植物の病気の原因は大きくは三つです。 まずカビ類の仲間である糸状菌によるものと細菌によるもので、いずれも伝染病です。 この二つの原因によって、使う薬品の種類が違うので注意が必要です。 さらに、ウイルスによる伝染病です。モザイク病などがありますが、これは芽の先が縮れたり葉が細かくモザイクのようなまだら模様になったりするものです。日に透かしてみると、その症状がわかります。この病気にかかっても、すぐに枯れることはありませんが、少しずつ株が弱って、やがて枯れてしまいます。ところが、このウイルスによる病気に効く薬剤はありません。そのため、病気にかからないように予防することが必要です。 予防の方法については、カビ類や細菌が原因となるものと同じですが、特にアブラムシの発生を抑える必要があります。 また、発生したらすぐに防除することも大切です。 球根の場合では、浅く植えすぎると、この病気にかかりやすくなります。 | |
| 薬剤の種類 | |
| 病気を治療する薬剤が、殺菌剤と呼ばれるものです。 薬剤にはさまざまな種類がありますが、大別するとカビ類が原因となる病気に効く薬剤と、細菌が原因となる病気に効く薬剤に分けられます。 <カビ類が原因の病気に効く薬剤> 「ダイセン」「ベンレート」「ダコニール」「トップジン」などの薬剤がたくさんあります。 それぞれ、どんな病気なのかによって効力に差があります。 <細菌が原因となる病気に効く薬剤> 細菌が原因となる病気には、軟腐病が代表的なものとしてあげられます。 これに対しては、医薬品としても使われているストレプトマイシンを成分とする薬剤を使わないと効果が表れません。 ところが、異常が見られている植物の病気の原因が、カビ類なのか細菌なのかの見分けは初心者でなくてもなかなか判断がつけにくいものです。 そのうえ、例えばシャクナゲによく発生する根腐れ病には、両方の原因が考えられるということもあります。 そこで、まずカビ類が原因となる病気に効く薬剤を使い、効果が上がらない場合は次に細菌が原因となる病気に効く薬剤を使うという方法をとるようにします。 あるいは、この2種類の薬は混合することができますから、判断をつけにくい場合に、はじめから混合して散布するという方法をとるようにします。 なお、病気に対する殺菌剤は、予防効果があります。従って、病気の発生前に最低量をほどこすということも考えておくとよいでしょう。 | |
【 植物に発生する害虫 】 | |
| 早期発見が一番 | |
| 病気には薬剤の散布が予防効果を発揮するのに対し、害虫に対しては薬剤は予防効果がありません。 これは、現在、出回っている薬剤の多くが直接害虫にかからない限り効果が表れないからです。 そういう意味では、まず、宝虫の発生しない環境づくりが大切だということになります。 また、宝虫が発生したら数が少ないうちに退治しておくという姿勢も必要です。 アブラムシなどは、数匹発生したなと思っていると、1週間もたたないうちに天文学的な数にふえてしまいます。 | |
| 害虫には2種類あり薬剤も2種類ある | |
| 害虫は、被害の及ぼし方によって主として2種類に分かれます。 一つがアオムシやケムシなどのような食害性の害虫で、葉などを食い荒らします。 アブラムシやダニなどのように、吸汁性と呼ばれている種類がもう一つです。 この二つの種類の害虫に対する薬剤は、それぞれ異なりますから、使い分ける必要があります。 食害性の害虫に対しては「スミチオン」など、吸汁性の害虫に対しては「マラソン」などが効果を発揮します。 ただし、アブラナ科の植物に対しては「スミチオン」は使えません。植物そのものに害を及ぼすからで、その場合は、「サイアノックス乳剤」を利用します。 なお、「スミチオン」と「マラソン」を混合した「スミソン」という薬剤があります。これを使えば、両方の害虫に有効です。 | |
【 病害虫の発生しない環境をつくる 】 | |
| よい土づくりで発生を抑える | |
| 花壇などの露地栽培とコンテナ栽培に共通していえる効果的な病虫害対策は土づくりで、これはガーデニングの基本です。 これにより、消極的ながら病害虫を防ぐことができます。 健康な土は、団粒構造で空気の通りも水はけも良いものです。 こうした土中の環境は、病原菌や害虫が最も嫌う環境だからです。 土の改良に役立つ微生物もたくさんいて、悪さをする微生物のはびこる余地はないのです。 よい土づくりのためには、花壇などの露地栽培では、植えつけの前に堆肥をたっぷりと入れるなどしてよく耕し、根の伸びやすい土にしてやります。 苦土石灰などを入れて酸度調整をすることも大切です。 また、元肥を適切にほどこしておくことも、健康な植物を育てるためには重要です。 | |
| 菜園などでは緑肥を入れると効果的 | |
| 主として菜園などでの野菜づくりのときに、有効な病害虫防除のやり方があります。 それは、緑肥をすき込むという方法です。 「緑肥」というように、肥料としての効果を期待するものですが、これによって土が改良され、センチュウなどの病害虫を抑えることにもつながっていきます。 よく利用されるのが、マリーゴールドやクローバー、ムギ、トウモロコシなどです。 緑肥用として園芸店などで販売されているものを利用します。 これらの種をまいて育て、種がつく前に刈ってそのまま土の中にすき込みます。 1~2か月で堆肥化しますから、春にまいて夏にすき込めば、9月からの秋野菜の種まきに間に合います。 特に、センチュウの防止に役立つのはマリーゴールドです。 | |
| 人間が快適な環境にしてやる | |
| 人間が快適だと感じる環境・・これは、植物にとっても同様に居心地よく育ってくれる環境です。 これを前提にして考えれば、どのような環境づくりをすればよいか、おのずからわかってきます。 人間と同様に植物も、ぎゅうぎゅうに混み合った場所は大嫌いです。 株と株が重なり合うようにして植えられていると、風通しが悪くなり、病気が発生しやすくなります。 陽当たりも悪くなってしまいます。 適切な間隔をおいて植えること。これが何より大切です。 また、特に庭木などでは、整枝・剪定という作業が重要です。 これも、樹形を整えるという目的のほかに、風通しをよくし陽当たりを確保するためのもの、つまり病気や害虫の予防をはかってのことだといえるのです。 | |
| 常に清潔に保つ | |
| 人間が体を不潔にしておくとよくないように、植物も株をいつもきれいにしておかないと、病害虫が発生しやすくなります。 特に問題となるのが、枯れた葉や茎をそのままにしておくことです。 これらは死んだところですから、そこから腐敗が始まります。 そして、病気に最初に狙われやすくなるのです。 多くの場合、下葉/株の地表近くから枯れ込んできますから、葉が黄ばんできたら早めに取り除いておきます。 もちろん、咲き終わった花も例外ではなく、すぐに花がらを取り除くことが必要です。 もう一つ大切なことは、雑草をはびこらせないという点です。 雑草は、風通しや陽当たりを悪くさせ、病原菌や害虫がつきやすくしてしまいます。 | |
| 容器栽培ならではの対策を講じる | |
| 容器栽培では、露地栽培に比べると、病害虫を避けるために必要な対策がたくさんあります。 陽当たりや風通しの確保のほかに必要な対策について、植えつけから生長の各段階を追いながら説明しましょう。 ①容器・用土は清潔なものを植えつけに使う 容器や用土は、清潔なものを使います。 古い容器や用土には、病原菌や害虫の卵などが残っている可能性があります。 一度使った容器をふたたび利用するときには、充分に水洗いしたのち、日光消毒をしてください。 同時に、使用する園芸用具についても清潔なものを使いたいものです。 そのためには、使い終わったときに充分に水洗いしてよく乾かしてから収納するという習慣をつけるように心がけてください。 用土は、市販の園芸用の用土を新しく利用します。 古い用土を再利用する場合には、充分に再生処置をほどこしてから使います。 ②種や苗は病書虫のないものを 当然のことですが、病原菌や害虫のついた種や苗をまいたり植えつけたりすると、そのものだけではなく、周囲の株にまで被害を広げてしまいます。 種や苗は、信頼できる販売店で買い求めることが大切です。 また、苗を購入するときは、葉の裏に害虫や卵が潜んでいないか注意するとともに、葉の一部が黒ずんでいるなどの病気がないか確かめる必要があります。 ③地面の上に直接置かない 種をまいたり、苗を植えつけたりした鉢やプランターなどの容器は、地面の上には直接置かないようにします。 土から伝染する病気の菌が鉢穴や排水口から入り込んでしまうからです。 これを避けるために、ブロックの上にのせたり鉢棚にのせたりするなどしてください。 ④ハダニとアブラムシにアルミ箔 害虫の中でもよくみられるものにハダニとアブラムシがいます。 主として葉の裏に繁殖して、汁を吸うなどの害を与えます。 このハダニとアブラムシ対策に効果的なのがアルミ箔。ハダニやアブラムシは直射日光を嫌います。 アルミ箔を鉢やプランターなどの容器に敷いておくと日光が反射して葉裏に届きますから、それを嫌ってハダニやアブラムシが寄りつかないというわけです。 | |
【 早期発見/対策 】 | |
| 兆しが見えたらすぐにもとを取り除く | |
| どんなに万全だと思える対策を講じていても、病気や害虫は発生してしまうものです。 人間の病気でも、早期発見・治療が最も効果的で、庭木・植物の病害虫にしても同様です。 病気や害虫の兆しが見えたら、すぐに的確な対策をほどこすこのことが、その後の被害の拡大を防ぐことにつながります。 まず、病気の兆しが見えた場合は、葉などの場合では、その葉をすぐに消毒します。 そのまま放っておくと、すぐにほかの葉へと伝染してしまうからです。 すでに害が広がっていれば、その株すべてを抜き取ってしまいます。 その株は、伝染のもととなるので、すぐに焼き捨ててしまうということも大切です。 また、害虫の場合も、見つけたらすぐに取り除くということが第一の対策です。 小さい害虫はこすり落とします。 大きなものは、手で取り除きます。 いずれにしても、ケムシなどのように、害虫によっては触れるとその部分がかぶれるなどする場合がありますから、軍手をはめてこすりとったり、使用済みの割り箸などではさんでとったりします。 なお、使った割り箸も捨てるようにしてください。 軍手などは、よく洗います。 | |
【 雑草の種類と対策 】 | |
| 庭での雑草の位置づけ | |
| 雑草というのは、農業の分野ではかなり厳密に種類が決められています。 基本的には作物の生育を阻害する植物として位置づけられています。 これに対して、庭での雑草の位置づけは、“鑑賞の対象となるかどうか”で決まります。たとえば、春に咲くタンポポでさえ、まとめ植えすると異色の花壇ができるかもしれません。 要するに、観賞しようとする草花以外の植物が雑草=不要な植物だということになります。 | |
| 一年草・ニ年草よりも多年草に悩まされる | |
| 雑草対策で最大の方法は、1週間に1回でも庭に出て、見つけしだい抜くということです。 春に生育する一年草・二年草の雑草は、このやり方で解決できるでしょう。 問題となるのは、その後に生育する多年草です。 これは、根茎を地下に伸ばしてそこから発芽してきます。 ですから、あっという問に広がってしまいます。 多年草は、地上に出ている部分を抜くだけでは根絶できません。 根茎が少しでも残っていると、再びそこから発芽していつまでも「イタチごっこ」が続きます。 | |
| 市販の小型の「三角ホー」を使ってかきとる | |
| 雑草をとるときは手で抜きとる方法もありますが、園芸店やホームセンターなどで市販されている小型の「三角ホー」を使うと便利です。 片手で持って、カマで刈るようにかいていきます。 一年草や二年草の小さいうちならば、表面を軽くかく程度で、根も取り除くことができます。 多年草のように、地中に根茎がある場合は、根元の部分に少し突き立てるようにして引き上げると、根茎もずるずるっと出てきます。 これを切りとらずに地中にたぐっていき、できるだけたくさん根茎をとるようにします。 | |
| 雑草で堆肥づくりをするときは要注意 | |
| 雑草を大量に刈りとったときに、それを積み上げて堆肥にするという例をよく見かけますが、注意しなくてはならないことが一つあります。 堆肥の材料にするときは、種ができる前に刈った雑草を使うということです。 雑草は生命力が旺盛ですから、種は堆肥にした場合でも生き残り、施したところで再び発芽してきて悩まされます。 | |
【 雑草対策のポイント 】 | |
| 根こそぎ引き抜くこと | |
| 雑草対策ということになると、その方法は、基本的には二つのやり方しかありません。 一つは「ただひたすら抜く」ことであり、もう一つは「薬品を使う」方法です。 雑草を抜くポイントは、必ず根こそぎ抜くということです。 雑草は非常に生命力が旺盛ですから、根が少しでも残っているとまた生長してしまいます。 まして、カマなどで「草を刈る」程度では、地表部分を取り除くだけですからまったく意味がありません。 これらの用具を使う場合でも、必ず土の中へ差し込み、広範囲に広がっている地下茎や根も一緒に取り除いてください。 | |
| 種ができる前に抜いてしまうこと | |
| 雑草とりでは、もう一つ注意したいことがあります。 それは、種ができる前にとることです。 種ができてしまうと、たとえその雑草を抜いたとしてもこぼれ種によってふたたび発芽してしまいます。 それも、より広範囲に広がってしまいがちです。 また、雑草を堆肥の材料として利用する人をよく見かけます。 しかし、この場合も、種ができる前に刈った雑草を利用しなければなりません。 種ができていると、たとえ堆肥化しても生き残った種から発芽してしまいます。 | |
【 除草剤を使った雑草対策 】 | |
| 除草剤はたくさん使っても効果は上がらない | |
| 市販されている除草剤を使う場合、一番注意したいのは、早く取り除きたいからと取扱説明書に書かれている使用量以上に使っても、効果は上がらないということです。 場合によっては、弊害が起こることさえあります。 これを踏まえて正しく除草剤を使っている限り、決して害を及ぼすということはありません。 | |
| 状況に応じて使い分けるとよい除草剤 | |
| 除草剤には二つのタイプがあります。 雑草が発生してから使うタイプと発生する前に使うタイプです。 発生してから使うタイプには、水溶液で使うものとエアゾールに入っているものがあります。 広範囲の雑草を対象にする場合は水溶液タイプがよく、少ない雑草を取り除くときはエアゾールタイプが向いています。 発生する前に使うタイプは、どのような場合に使うのがよいのでしょうか。 一つは、前年に大量に雑草が発生した場合などがあります。 そういう場所にはこぼれ種によって、再び出てくる恐れがあります。 あるいは、長期間にわたって留守にして雑草とりができないような場合です。 発生前に使うタイプは、主として粒状になっています。これを広さに応じた適切な量でまくようにします。 | |
【 除草剤の使い方 】 | |
| 人体に危険なものもあることを知っておく | |
| 除草剤の中には人体に危険なものもあります。 雑草に悩まされ続けると、つい強い薬を使いたくなります。 強い薬であればあるほど、使い方を誤ると人体にも悪影響を及ぼしてしまいます。 たとえ「家庭園芸用」の除草剤であっても、誤った使い方をすると大変です。 長期に雑草取りができないなどの、やむを得ない場合以外は、原始的ではあっても「手で抜くこと」が確実で安全な雑草対策であることだけは念頭に置いておきたいものです。 | |
| 除草剤の種類 | |
| 市販されている薬品にはほどこす時期やほどこし方によっていくつかのタイプがあり、それぞれ目的や使い方が異なっています。 市販の家庭園芸用の除草剤の主な種類と特徴、使い方のポイントなどを説明しましょう。 ①選択性除草剤 「2・4D」が代表的なもので、多くは、広葉雑草に効果のある除草剤です。 イネ科植物には効果がないという特徴があります。 この性質を利用して、イネ科の芝生に生える雑草の除草に使われます。 ②非選択性除草剤 すべての植物を枯らす除草剤です。 「レグロックス」や「グラモキソン」のように、ほどこしたのちすぐに分解してしまうタイプと、ほどこしてから1年以上も分解しないタイプ(「クサトール」など)の2種類があります。 すぐに分解するタイプは、庭などでの除草に使うことができます。 しかし、すぐに分解しないタイプは、庭などに使うとほかの植物も枯らしてしまいます。 このタイプは、空き地の除草などによく使われているものです。 ③発芽抑制型除草剤 「シマジン」が代表的なものです。雑草の種が発芽するのを抑制する働きがあります。 あらかじめ雑草がたくさん生えそうなところなどにほどこしておく、というような使い方をします。 | |
| 雑草対策/害虫対策ページへジャンプ | |
| 病害虫駆除の豆知識へジャンプ | |