【 庭木の剪定 】 | |
| 庭木は生き物ですから日々成長していきます。 植えた直後とは違って、放っておくと横にも縦にも大きくなりすぎたり、葉が茂りすぎて邪魔になったりしてくるものです。適切で定期的な管理と手入れで、いつも整った樹形の庭木を保つ方法をご説明します。 | |
| 適切な時期に正しい剪定を行なう | 草花を植えた花壇の場合ならば、(宿根草は別としても、)一年草などは半年〜1年のサイクルで生育→枯死を繰り返しますから、日常的に水やりや雑草除去はあるにしても、管理そのものはそれほど難しくはありません。 ところが、庭木の場合には、草花と異なって(1年サイクルではなく)何年もかけて徐々に生長していきます。 ですから、一旦植えた庭木が大きくなりすぎないよう、加えて、形のよい状態で生長させるためにも、適切な管理は欠かせないところです。 整枝や剪定と言って、枝を切るなどして樹形をきれいに整えていく作業のことを言います。 しかし、大きくなりすぎたからと幹の途中から切り落としてしまったり、形が気に入らないからといって闇雲に枝を切り落としたりしては庭木に対して悪影響となります。 「適切な時期」に「正しいやり方」で整枝・剪定を行なっていくことで、自分の思うような状態に育ってくれるのです。 |
【 実際の庭木剪定 】 | |
| 庭に植えたシマトネリコ(左)とヤマボウシ(右)です。 春になって庭木も成長が活発になると、ご覧のように伸び放題に茂ってしまいます。 | |
| <高いところの作業> シマトネリコのような背の高い庭木は、ご覧のようにハシゴを使って上部を剪定していきます。 枝の細い庭木であれば”高枝バサミ"などで剪定できますが、それでも枝の太い部分はハシゴを使って(時には)鋸で切断します。 | |
| <残骸??> (ちょっと見難いかもしれませんが)剪定した後の"残骸”で、このような有様になります。 バッサリと枝を切るまではいいのですが、実は切り落とした枝葉の後始末も結構重労働です。 | |
| 上の欄で紹介したシマトネリコ(左)とヤマボウシ(右)ですが、剪定した後の様子です。高さだけでなく横に伸びた無駄な枝、または生茂った葉を剪定してスッキリした樹形になりました。 | |
【 育ち過ぎた庭木の剪定 】 | |
| 剪定と刈り込みは違う | 一口に整枝・剪定といいますが、これらは二つに分けて考えます。 一つは、庭木の成木状態をそのまま小型化した形に整えるやり方となります。つまり、自然に近い状態に仕立てていく方法とも言え、一般的な家庭でのやり方です。 多くの樹木は放っておくと毎年毎年スクスクと生長していき、種類によっては数メートル〜10数メートルにもなっていきます。 それを自分の庭のスペースに合わせ、バランスを整えるのが整枝・剪定ということになります。 もう一つは、庭木をまったく人工的な形に整えるやり方です。いかにも“庭師”など職人の方が手入れしたような和風の庭でよく見られますよね。 そうした庭では例えば、生け垣では、直線的なものあるいは曲線の連続した形に仕立てたものが見られます。 洋風の庭では、動物やその他のものをかた取った(※トピアリーと呼びます)、まるでオブジェのような形に仕立てたものもあります。 こうした作業は、整枝・剪定というよりは、むすろ刈り込みと呼ばれるのが一般的かと思います。 整枝・剪定は、それぞれの樹木の性質によって適切な時期とやり方があります。これに対して刈り込みのほうは、一般的に強健な樹種を用いることが多く、切っても切ってもすぐに発芽してきますから、小まめに刈り込む必要があります。また、これによって樹木は密生しますから、形もよりきれいに仕上がります。 |
| 樹木の種類別にみた整枝・剪定の適期 | 樹木には、落葉樹と常緑樹、また針葉樹や広葉樹などの種類があります。 また、花の咲くのを楽しむ樹木もあります。 この中で、花を楽しむものは別として、そのほかの樹木については、原則として3〜4月に剪定するのが最適です。 気温の上昇とともに、この時期から新芽が伸び始めるため、形を整えるのには絶好の時期なのです。 このほかには、6〜7月、10月中旬〜12月も整枝・剪定を行なうことができます。 花の咲く樹木は、花が咲くために、花芽ができ始める時期があります。 この時期の違いによって、整枝・剪定の時期が異なってきます。この時期を誤ると、せっかくの花芽を切り落とすことになり、花を楽しむことができません。 |
| 花後に行なうもの | 昨年伸びた枝に花芽がつき、そこに花が咲く種類があります。 ウメやモモ、サクラなどが該当します。 また、昨年伸びた枝に花芽がつきますが、そこからさらに伸びて花が咲くものもあります。 アジサイやコデマリ、ツツジ、サツキなどです。 これらについては、花の咲く前に整枝・剪定すると花芽のついた枝を落としてしまうことになり、花が咲かなくなってしまいます。 従って、整枝・剪定は花の咲き終わった直後に行ないます。 |
| 晩秋〜早春に行なうもの | その年に伸びた枝に花芽ができ、その年のうちに花が咲く樹木の場合は、整枝・剪定は晩秋から翌年の春、新しい芽が出る前に行ないます。 |
【 庭木:切り落とす必要のある枝を切る 】 | |
| 整枝・剪定といっても、闇雲に枝を切っては逆効果になってしまいます。 樹木の枝には、切ってはならない枝と、切り落とさなくてはならない枝があります。 | |
| 切ってはならない枝 | 幹や主枝や副枝など主だった枝やそれから出ている太めの枝があります。 いわば、その樹木の骨組みを構成するものだと考えてよいでしょう。 これらは、太いのでうっかり切り落とすということはありませんが、樹形を変えようとして切ってしまう場合がありますから、注意しなくてはなりません。 樹形を変える場合は、新しい主枝や副枝を充分に育ててから古い主枝・副枝を切るようにするのです。 また、同様に樹木の全体の形をつくっているような枝も残さなくてはなりません。 さらに、その年に伸びた新しい枝の先端の部分も残します。 |
| 切り落とさなくてはならない枝 | 樹木の形を損なうような枝があり、これらを切り落とすことは必要ですが、さらには、樹木の生育をはばんでしまうような無駄な枝というものもあります。 こうした枝を剪定の対象として適期に整理するようにしましょう。 <幹吹き> 樹木が弱ってくると、よく出る小枝です。根から吸い上げられた養分が樹木の先まで昇りきらないために、下のほうにたくさんの小枝を出してしまいます。放っておくとますます樹木は弱まってしまいます。 <枯れ枝> そのまま放っておいても、生長しない枝です。切り落とさないと病害虫発生の原因となります。 <からみ枝> 枝が伸び、近くの枝同士がからみ合ってしまっているものをいいます。混み枝ともいいます。 <徒長枝> 他に比べて特に勢いが強く、太く、長く伸びすぎている枝のことをいいます。 |
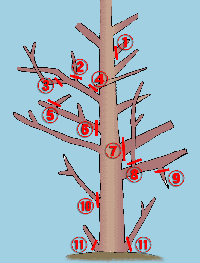 |
樹木は放っておくと無駄な枝や葉を付け、その庭木だけでなく庭そのもののバランスを崩します。また、花や実をつけさせたり、病害虫の寄生を抑制したり、時には防風や防音の目的などで、ガーデニングでは定期的に剪定をしなければなりません。しかしこの剪定作業は初心者には意外と難しく、どこをどの程度切っていいものか・・迷うところですね。 下記に初心者がご自分で剪定される際に、どの部分の枝を切ればよいのかポイントを記しておきます。 <1>樹幹から伸びた枝 <2>横に広がらずに真っ直ぐに伸びた枝 <3>絡まった枝 <4>他の枝と交差した枝 <5>幹の方へ伸びた枝 <6>幾つもの枝が平行に伸びた場合は、その中から不要な枝 <7>主幹を突きぬくように左右に伸びた枝 <8>大きくバランスを崩す枝 <9>下に垂れた枝 <10>樹木の根元部分から伸びた枝 <11>樹木の根元から出ている細い枝 |
【 庭木の刈込み 】 | |
| 見苦しい!樹形の乱れた生け垣やトピアリー | きれいに刈り込まれた生け垣は、見ていても大変に気持ちのよいものです。 その半面、樹形が乱れてしまったものは、見苦しいばかりか、手入れも手間がかかって大変です。 また、洋風の庭によく置かれるトピアリーも、形が整っていれば見ていて面白いものですが、形が崩れてしまってはどうしようもありません。 この点では、生け垣以上に始末に困ります。 このようなことを防ぐためには、日常的な刈り込み作業が欠かせません。 小さい枝が少しでも伸び始めてきたら、すぐに刈り込むくらいの気持ちで、毎日点検します。 |
| 形が整うまでは年に2回以上刈り込む | 生け垣やトピアリーも、一般の樹木と同じように、陽当たりの確保や風通しをよくする必要があります。 そのため、毎年1回は整枝・剪定作業が必要です。 例えば、生け垣の場合では、形が整うまでは、年に2回ぐらい整枝・剪定を行ない、ある程度形が整っても、毎年の整枝・剪定は欠かさず行ないます。 刈り込みは、市販されている刈り込みバサミを使って行ないます。 刃が湾曲してついているものは、通常平たく刈り込むときは湾曲面を上にして使います。 曲面を刈り込むときには湾曲面を下向きにし、曲面に合わせるように使います。 |
【 庭木を植え替える 】 | |
| 建物を和風から洋風へ改築したときなど、それまであった庭も、それに合わせてつくりかえたいものです。 そういう場合には決まって、大きな庭木を植え替えることが難題としてのしかかります。 そこまでいかなくても、庭木の植え替えというのは、案外よく直面するものです。 いずれにしても、庭木の植え替えというのは、いきなり掘り上げて別の場所に穴を掘って植えつけるというわけにはいかないのが厄介です。 ただし、せいぜい1m程度のものまでなら、思い立ったその日にでも植え替えることは可能です。 ただし、植え替えの適期というものがありますから、その辺の調整は必要です。 落葉樹は、葉のない休眠中が適期です。 だいたい11月から翌年の3月ごろまでとなります。 これに対して常緑樹は、地温の高い時期が適期で、酷暑の8月を避けた6月下旬から9月の間です。 | |
| 小形の庭木なら掘り上げてすぐ植えつける | 樹高が1m程度までの場合は、掘り上げてすぐに手早く植えつければ活着し、失敗は少ないといえます。 準備として、枝の切り詰め作業を行なっておきます。これは、根をかなり切るため、地上とのバランスをとる必要があるからです。 その後、植え替え作業がやりやすいように枝をまとめて縄などでとめておきます。 掘り上げは、幹のまわりに幹の直径の3〜4倍程度の円を描き、その外側にぐるりと溝をつくるように掘り下げます。 このとき、横に張っている根にスコップがあたりますが、ノコギリでこれを切っていきます。 さらに、樹木の底のほうも掘り、株全体を掘り上げます。 掘り上げたら、根のまわりについている土を絶対に崩さないようにします。 とりわけ常緑樹は要注意です。 そして、できるだけ速やかに新しい場所に植えつけます。 |
| 大形の庭木は事前にじっくりと根回しをする | 大形の樹木の植え替えは、なかなか厄介です。 まず、植え替えの時期を決める必要があります。これは小形の樹木と同様で、落葉樹は、葉のない休眠中11月から翌年の3月ごろまで)が適期です。 常緑樹は、8月を避けた6月下旬から9月の間です。 植えつけの時期は、半年から1年前に決めなくてはなりません。 そして、根回しと呼ばれる作業を行なうのです(※ものごとをスムーズに決定するために、関係各方面にあらかじめ話を通しておくステップを根回しと呼びますが、植え替えのときの根回しが転じたものです)。 つまり、植え替えの時期までに、植え替えが失敗しないように充分準備をしておく必要があります。 大形の樹木の植え替えは半年から1年がかりで行なうわけです。 根回しは、次のような段取りで行ないます。 <1:幹の周囲に溝を掘る> 幹の直径の5倍程度の直径の円を、幹の周囲に描きます。 その円の外側に、スコップで溝を掘ります。 <2:横根の皮をはがす> 掘り下げるに従って、横に張った太い根が現れますが、その根は切らず、根の皮だけをはがします。 横根がなくなったら掘るのをやめます。 <3:埋め戻して細根を発生させる>いったん埋め戻します。できれば、肥料分のたっぷりと入った土を用いるとよいでしょう。こうすることで、横根の皮をはがしたところに細根が盛んに発生します。 植え替えの時期までには、新しい環境で充分に活着するだけの細根が生長します。 根回しの大切さは、ここにあるわのです。 【植えつけは手早く行なう】 植えつけの時期がきたら、まず、新しい場所に植え穴を掘っておきます。 大きさは、根回しのときに掘った溝の外側の直径よりも大きめとします。深さは溝の深さよりも深めにします。 植え穴が掘れたら掘り上げます。根回しのときに掘った溝の外側に沿って、スコップを入れて掘るようにします。 これによって、半年〜1年間に発生した細根をそのまま掘り上げることになるのです。 掘り上げた株は、根のまわりについた土を絶対に崩さないようにして、新しい植え穴に、すぐに入れて植えつけます。 新しい植え穴の場所が離れているときや、根のまわりの土が崩れそうなときには、掘り上げたときに土のまわりにワラ縄を巻いて土が落ちないようにします。 植えつけのやり方は、樹種によって「水ぎめ法」「土ぎめ法」で行ないます。 また、必要に応じて支柱を立て、しっかりと固定するようにします。 【植え替えが終わったら思いきって切り詰める】 植え替えが終わった直後は、根が活着していません。そのため、水分が蒸散しても、根からは充分な養分や水分が上がらず、うまく活着しないことがあります。 そこで、根からの吸い上げの量に応じて、上部を切り詰めてやる必要があります。 落葉樹は全体の3分のーくらい、常緑樹は葉が茂っていますから思いきって3分の2ほど切り詰めます。 |
【 コニファーの剪定 】 ※初心者からベテランまでガーデニングの人気者コニファー | |
 |
イングリッシュガーデンや生垣など多彩な場所に植えられるコニファーは、ガーデニング初心者からプロまで誰もが好んで植える庭木です。 このコニファーの特徴は ハサミなど金物で剪定すると、切り口が茶色に変色することです。なので、できれば3月くらいの新緑が芽吹く前に剪定し、なるべく早めに切り口が隠れるようにします。 |
| コニファーの剪定時期 | 3月から9月くらいまで剪定できますが、コニファーの枝には若い枝と木質化した枝がありますので、(若い枝はどこで切っても構いませんが)木質化した枝は必ず小枝を残すようにします。 |
| コニファー剪定の注意事項 | ・コニファーには種類によって剪定時期が違います。 ・出来る限り「手摘み」をすれば変色する心配が少なくなります。 ・コニファーを刈り込んだ後は必ず木を揺さぶって切った枝をふるい落とします。これをしないで、切った枝が内部に残っていると病害虫の原因になったり、変色したりします。 |
【 主な庭木の剪定時期 】 | |
| あじさい | <剪定時期> 秋を過ぎて剪定すると花がつきませんので、花後スグに剪定する必要があります。 |
| キンモクセイ | <剪定時期> 花後から春先までに剪定します。夏に切ると枝が枯れることがあります。 |
| コデマリ | <剪定時期> 花後に枝の別れ部分で切ります。 |
| サザンカ | <剪定時期> 花後から春先までに剪定します。 |
| サルスベリ | <剪定時期> 萌芽前(3月頃)に、前の年に伸びた枝を付け根まで剪定します。 |
| ツツジ | <剪定時期> 花後スグに刈り込んで整形します。 |
| ハナミズキ | <剪定時期> 花芽がついていない細い枝等を休眠期に剪定します。 |
| モクレン | <剪定時期> 花後と休眠期に枝の付け根から剪定します。 |
| ユキヤナギ | <剪定時期> 花後すぐに伸びすぎた枝を切り戻します。 |