【 庭木の植え方:常緑樹と落葉樹の植えつけ時期 】 | |
| 常緑樹は春秋の彼岸が過ぎてから植える |
常緑樹 例えば、春に新しい芽が出る前に植えつけると、株が根づくまでに時間がかかりますから、その後の新芽の伸張に悪い影響を及ぼしてしまいます。そのため、春に常緑樹を植えつける場合は、新芽が出始める直前が適していることがわかります。 具体的には、春の彼岸過ぎから4月上旬ということになります(※地域によって温度は大きく異なりるため、ソメイヨシノの開花を基準とするとよいでしょう)。「常緑樹は針葉樹を含め、植えつける場所の周囲でソメイヨシノが開花する前後に植えつける」ということがポイントとなります。 一方、秋も植えつけるとができます。「秋の彼岸過ぎから10月中旬」が適期です。 常緑樹は冬の間も葉をつけて、葉から水分が蒸散しているため、植えつけ時期が遅れれば遅れるほど根張りも遅れてしまい、充分な水分を吸い上げられなくなります。 その結果、株に悪い影響を与えてしまいます。たとえば、半月遅れて11月に植えると、3月になってから枯れてしまうこともありますから、時期を逸しないようにしたいものです。 なお、植え替えについても、春、秋ともに同じ時期が作業の適期となります。 |
| 落葉樹は早春と晩秋が植えつけ適期 | 常緑樹に対して落葉樹の場合は、葉が落ちますから、その間であれば、水分の蒸散による株への悪影響を避けることができます。なので、「春は新芽が動き始める前の2月、秋は落葉後の11月に植えつける」のが適しています。また、これらの時期は、挿し木の適期ともなっています。 |
| 絶対に植え替えてはいけない時期 | 樹木の場合、春から夏にかけて新芽を伸ばして旺盛に生長します。 そのため、梅雨のころには株が非常に柔軟な状態になっています。このときに植え替えを行なうと、根の切断により吸水が悪くなり、株を傷めてしまうことになります。ですので庭木の植え替えは梅雨の間に行なってはいけません。 逆に、株がやわらかいという点に注目すれば、常緑樹は挿し木を行なうのに適していることになります。また最も生育の旺盛な時期にあたる真夏は、同じく庭木の植え替えを避けるのが得策です。 |
【 庭木の植え方 】 | |
| 苗木の選び方 |
<苗木は根と幹を見て善し悪しを見分ける> 苗木 <元気のよい根を持つ苗木を選ぷ> 普通、苗木は樹高が高くなるものでも1.5mくらいまでのものが販売されています。苗木の根の部分のまわりは「根巻き(※土をつけてワラやコモで覆う)」して販売されているのが普通です。 上部がいかに形がよいものでも、根に元気がなければ、やがて枯れてしまいます。そこで、苗木の上部を持って軽く揺すってみて幹の根元のところがグラグラしないもの、これが基本的にはよい苗木です。 しかし、根の部分が乾燥している苗木、これは絶対に避けなくてはなりません。 <幹が太く芽の大きい苗木を選ぷ> 地上部では、幹の比較的太いものがよい苗の条件です。苗木にはすでに芽がついていますが、それがしっかりとしているものなども、よい苗木の条件となります。 |
| 根鉢は絶対に乾かさない | 苗木を選ぶとき、根鉢が乾いていないことが条件となりますが、これは、運搬のときや保管しておく場合にもいえることです。 苗木の購入前に植える場所を決めておき、購入したらその日のうちに植えつけるのが理想的です。 もし、どうしても数日置いておかなくてはならなくなったら、根鉢を乾かさないようにするため、充分な管理をしなくてはなりません。根鉢の部分をさらに湿らせた新聞紙などで厚くおおって日陰に置き、乾かないように欠かさず水やりを行ないます。 こうすれば1週間程度は置いておけます。 |
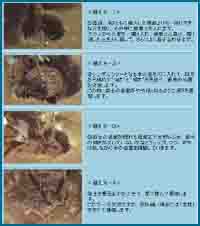 |
庭木植え方手順の写真での紹介は、シンボルツリーの植え方として掲載していますので、ご確認ください。。 |
【 2種類の庭木の植え方 】 | |
| 樹種によって異なる2種類の植え方 | 庭木の植えつけには、「水ぎめ法」と「土ぎめ法」の二つのやり方があります。 水ぎめ法はほとんどの樹種に共通した植え方です。土ぎめ法は主としてマツ類を植えつけるときに用いられる方法です。 いずれの方法も、植えつけのーか月くらい前までに、土づくりを済ませておく必要があります。 腐葉土か堆肥をたっぷりと入れ、元肥として1平方メートルあたりスコップー杯ほどの有機質肥料をほどこし、充分に耕しておくという作業です。 草花と違って樹木は、生育期間が長いため、ゆっくりと効く有機質肥料のほうが適しています。 また、この植えつけ段階で、樹木の向きを決めておくこともポイントです。植えつけてから向きを変えようとすると、根を傷つけてしまいます。 <水ぎめ法> ①まず、植え穴を掘ります。根鉢を入れたときに充分に余裕のあるくらいの、大きめの穴をあけることがポイントです。根鉢の直径の1.2~1.5倍が適当です。 ②苗木を植え穴から一旦出し、穴の底の中央部に土を盛ります。根鉢を再び入れ、その上部/幹のつけ根の部分が地表よりも少し上になるくらいの高さになるようにします。 ③埋め戻します。根鉢に巻かれていたコモやワラなどを取り除き、根鉢の土を少しつついておくと周囲の土によくなじみます。その後、スコップなどで根鉢の穴のすき間に八分目ほどの深さまで土を入れながら、ホースで水をたっぷりと注ぎ込みます。「この作業が水ぎめ法のポイント」となります。水は、根鉢の周囲がぬかるみ状態になるまで注ぎます。 ④その後、幹を持って苗木を軽く揺すり、水が植え穴の全体に回るようにします。棒などでつつきながら行なうと、より効果的です。苗木の位置や向きはこの段階までに正確に決めておきます。最後に、残りの土を埋め戻し、株の周囲をよく踏み固めておきます。 ⑤水やりをしたときに効果的に水が行き渡るよう、植え穴の縁あたりに15㎝ほどの高さの土盛り水鉢をぐるりとつくります。そこへ、たっぷりと水を注いでおきます。 ⑥最後に、成木では幹巻きをして支柱を立てます。幹巻きは、地上部分からの蒸散作用の負担が根にかからないようにするもので、特に常緑樹に必要です。これには、市販の幹巻き用のテープがあります。支柱は、小さい樹木の場合は1本、幹と平行に立てる程度で充分です。 <土ぎめ法> 水ぎめ法と基本的には同じプロセスをたどります。大きく違う点は、埋め戻すときに水を注ぎながら行なうか行なわないかということです。 土ぎめ法では、「埋め戻すときに水は入れない」のがポイントとなります。このときに、少し埋め戻しては棒などで突き固め、さらに土を少し入れるという作業を繰り返し、根と土の間にすき間ができないように注意することも大切です。 土を埋め戻したら、株の周囲をよく踏み固めておきます。 その後の、水鉢づくりや幹巻き、支柱立ては、水ぎめ法と同様にして行ないます。 |
【 大型の庭木の植え替え 】 | |
| 半年~1年前に根回しをする |
大型の樹木の植え替えは、なかなか厄介です。 植えつけの時期の半年から1年前に、「根回し」と呼ばれる作業を行なう必要があるからです。 大型の樹木は、根が非常に広い範囲に張っていきます。そのため、掘り上げるときによほど広く掘らないと、新しい場所で根づくだけの根が掘り上げられません。 実際問題としてそんなに広く掘り上げられるわけがなく、その為ある程度の広さで掘り上げても失敗しないように根回しを行なうのです。 根回しは、次のような段取りで行ないます。 ①幹の周囲に溝を掘る 幹の直径の5倍程度の直径の円を、幹の周囲に描きます。その円の外側に、スコップで溝を掘ります。 ②横根の皮をはがす 掘り下げるに従って、横に張った太い根が現れますが、その根は切らず、根の皮だけをはがします。木工用のカッターナイフなどを使うとよ.いでしょう。横根がなくなったら、掘るのをやめます。 ③埋め一戻して細根を発生させる いったん埋め戻します。できれば、肥料分のたっぷりと入った土を用いるとよいでしょう。こうすることで、横根の皮をはがしたところに細根が盛んに発生します。養分や水分を吸う力の最も強い細根が幹の直径の5倍の円周のところに沢山できることで、それよりも広い部分にある根を残して掘り上げて新しい場所に植え替えても、そこで充分に活着します。 |
| 植えつけは手早く行なう | 植えつけの時期がきたら、まず、新しい場所に植え穴を掘ります。 穴の大きさは、根回しのときに掘った溝の外側の直径よりも少し大きめとします。深さは溝の深さよりも深めにします。 植え穴が掘れたら、株を掘り上げます。根回しのときに掘った溝の外側に沿って、スコップを入れて掘るようにします。 これによって、半年~1年間に発生した細根をそのままそっくり掘り上げることになるのです。それより外側の根は、ノコギリなどで切り離します。 このとき、せっかく発生した細根を傷つけないように注意が必要です。 掘り上げた株は、根のまわりについた土を絶対に崩さないようにし、新しい植え穴にすぐに入れて植えつけます。 新しい植え穴の場所が離れているときや、根のまわりの土が崩れそうなときには、掘り上げたときに土のまわりにワラ縄を巻き、土が落ちないようにします。 植えつけのやり方は、樹種によって「水ぎめ法」あるいは「土ぎめ法」で行ないます。また、必要に応じて支柱を立て、しっかりと固定するようにします。 |
| 植え替え後に思いきって切り詰める | 植え替えが終わった直後は、根がまだ活着していません。そのため、地上部の葉などから水分が蒸散しても、根からは充分な養分や水分を補充できず、うまく活着しないことがあります。 そこで、根からの吸い上げの量に応じて、上部を切り詰めてやる必要があります。落葉樹は全体の3分のーくらい、常緑樹は葉が茂っていて蒸散もその分旺盛ですから、3~2分の1を切り詰め、混んだところも間引きます。 |